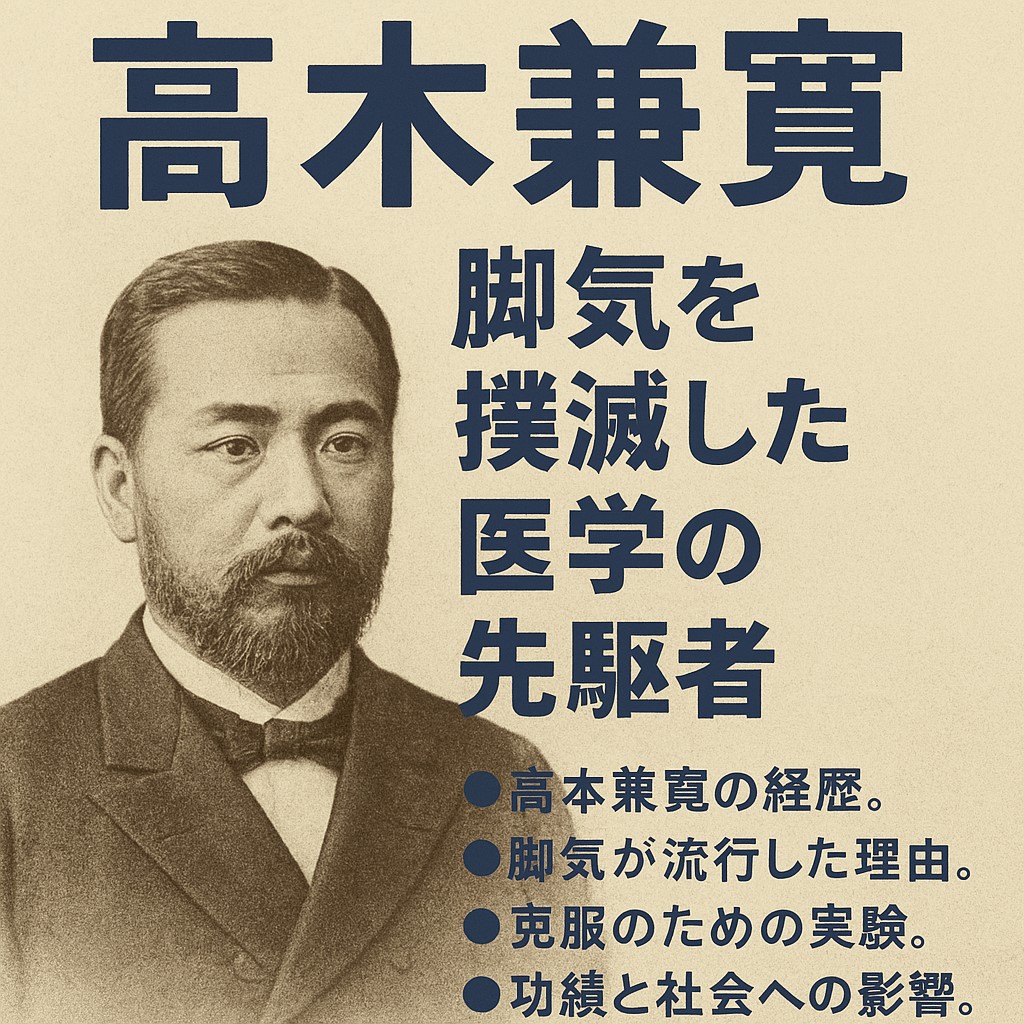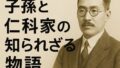「脚気(かっけ)」という病名を聞いたことがありますか?
現代ではあまり耳にしないかもしれませんが、かつて日本では深刻な国民病として多くの命を奪っていました。
特に明治時代の海軍では、原因不明の脚気が蔓延し、兵士の死亡率が高まる深刻な問題となっていたのです。
そんな中、「病気は栄養に関係しているのではないか」と、当時の常識に逆らって立ち上がった一人の医師がいました。
それが高木兼寛(たかぎ かねひろ)です。彼は海軍軍医として実証実験を重ね、脚気撲滅へと導いた先駆者でした。
この記事では、「高木兼寛 脚気を撲滅した医学の先駆者」というタイトルの通り、彼がどのように脚気と向き合い、日本の医学に革新をもたらしたのかをわかりやすく紹介していきます。
●高木兼寛が脚気撲滅に貢献した理由がわかる。
●白米中心の食生活と脚気の関係が理解できる。
●栄養学の重要性と高木の実証主義の姿勢が学べる。
●彼の功績が現代医療や予防医学にどうつながっているかがわかる。
高木兼寛とはどんな人物だったのか
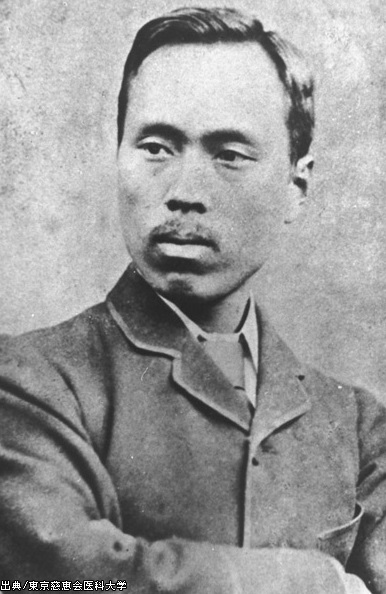
「脚気をなくした医師」として知られる高木兼寛(たかぎ かねひろ)は、明治時代の日本において医療改革を進めたパイオニアです。
彼は単なる医師にとどまらず、教育者、そして制度改革者としても多大な影響を残しました。特に日本海軍における兵士の健康管理や、後の慈恵医科大学(現・東京慈恵会医科大学)の創設者としてもその名は刻まれています。
そんな高木の人生を追ってみると、彼がどのような信念を持ち、なぜ「脚気撲滅」という歴史的功績にたどり着いたのかが見えてきます。
医学を志したきっかけと留学経験
高木兼寛は鹿児島県に生まれ、幼少期から学問に親しみました。やがて西洋医学に魅了され、東京医学校(現・東京大学医学部)を経て、さらに英国へ留学する機会を得ます。
この留学が彼の医学的視野を大きく広げることになりました。
当時の日本では、病気の原因は「体質」や「気候」によるものとされていましたが、高木はロンドンでの臨床教育を通じて、「病気の原因は生活や栄養にある」という近代医学の考え方に触れたのです。
帰国後、彼はこの経験を日本の医療に取り入れようと奮闘しました。
日本初の臨床教育と慈恵医大の設立
帰国後、高木は日本における臨床医学の導入に力を注ぎました。
それまでの医学教育は座学中心でしたが、彼は患者を診察しながら学ぶ「ベッドサイド教育」の重要性を説き、それを実践する場として、1881年に「有志共立東京病院(のちの慈恵医大)」を設立します。
この病院は、学問と実地医療が融合した教育機関として高く評価され、現在の東京慈恵会医科大学へとつながっています。
彼の人生は「西洋の医学知識を日本に根づかせる」ことに捧げられたともいえるでしょう。その延長線上に、後の「脚気撲滅」という日本の公衆衛生を変える大きな成果があったのです。
脚気とは?なぜ当時の大問題だったのか

「脚気(かっけ)」とは、足がしびれる・力が入らない・歩けなくなるといった症状に始まり、重症化すれば心不全で命を落とすことさえある病気です。
江戸から明治時代にかけて、日本ではこの脚気が広く蔓延し、特に軍隊や寄宿舎生活を送る若者の間で深刻な問題となっていました。
実際、明治時代には年間1,000人以上の死者が出ていた時期もあり、兵士たちの命を奪う「見えない敵」として恐れられていました。
その原因は、当時の主食である白米中心の食生活にあったのですが、当時の日本ではまだその因果関係は明確にされていなかったのです。
ビタミンの発見以前の常識
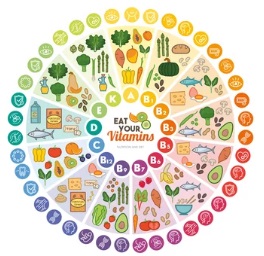
現代では、脚気は「ビタミンB1の欠乏症」であることがわかっています。
しかし当時は「病気=細菌や感染症が原因」という考えが主流であり、栄養不足が病気を引き起こすという認識はほとんどありませんでした。
白米にはビタミンB1がほとんど含まれておらず、しかも精米によってそのわずかな栄養素さえ削り取られてしまいます。
一方で、ぬか(米ぬか)を含んだ玄米や麦にはこの栄養素が豊富に含まれており、それが脚気予防に重要だったのですが、当時の人々はその事実に気づいていませんでした。
その結果、白米ばかり食べていた人々の間で脚気が多発し、とくに兵士や学生のように集団生活を送る人たちに深刻な影響が出たのです。
なぜ海軍と陸軍で結果が分かれたのか?
高木兼寛が脚気の予防に取り組んだのは、日本海軍の軍医として勤務していた時代のことです。当時、海軍では多くの兵士が脚気にかかり、遠征に耐えられず亡くなる者も出ていました。
そこで高木は、独自に麦飯を取り入れた食事改善を実施しました。
結果は驚くべきもので、脚気による死亡率は劇的に減少したのです。
この事実を裏付けるため、高木は「金剛艦」の遠洋航海で麦飯と野菜を積極的に取り入れた食事を導入し、帰還後の健康状態が非常に良好だったことから、麦飯こそが脚気予防の鍵であると証明しました。
一方、陸軍では当時の軍医トップであった森鷗外が「脚気は細菌感染によるもの」と主張し、白米中心の食事を続けました。その結果、脚気による死者は海軍の10倍以上ともいわれる状態が長く続きました。
この「海軍と陸軍の脚気対策の分かれ道」は、日本近代医学史における重要なエピソードとして今でも語り継がれています。
実験と実証主義で脚気を克服

脚気の正体がはっきりしない中で、多くの医師が原因を細菌や気候のせいと考えていた時代。
そんな常識にとらわれず、「現場で起きていることを、実際のデータで確かめよう」と考えた人物が、高木兼寛でした。
彼は海軍軍医として、兵士たちの命を守るべく、大規模な栄養実験と統計的な比較という手法で脚気の撲滅に挑みました。
白米と麦飯の船で比較した実験
1883年、高木は自らの仮説を証明するために、画期的な方法を実行に移しました。それが「食事の違いによる脚気の発生率の比較実験」です。
当時、海軍の遠洋航海では脚気による死者が続出しており、高木はこれを「白米ばかり食べることが原因ではないか」と考えていました。
そこで、艦隊のうち1隻には従来通り白米中心の食事を、もう1隻には麦飯と野菜を多めにした食事を与えて遠洋航海を行いました。
その結果、白米の艦では多くの脚気患者が出た一方で、麦飯の艦ではほぼゼロ。死亡者数にも大きな差が生じたのです。
この明確な差により、高木は「食生活の改善こそが脚気の予防になる」という結論を導き出しました。
医師ではなく“科学者”としての視点
この時代、日本では「経験則」や「権威」が重視され、医学的な知識も欧米の翻訳に頼るばかりでした。しかし高木は、英国留学で学んだ近代医学の「実験・検証・統計」の重要性を理解していました。
彼が用いた手法は、いわば「現代のエビデンス・ベースド・メディスン(EBM)」の先駆けと言えるものです。
脚気の原因がまだビタミンB1の欠乏だとは分かっていなかったにも関わらず、「麦飯を食べると脚気にならない」という事実をデータで示し、周囲を納得させたのです。
当時の主流派である陸軍医官・森鷗外が「脚気は感染症である」と主張し続けたのに対し、高木は科学者としての冷静な視点で反論を展開。
陸軍と海軍で脚気対策に大きな差が生まれたことは、医学史における象徴的な対立としても知られています。
このように、高木兼寛は医師である以前に、「科学的思考」を日本に持ち込んだ人物として、その先進性が高く評価されています。
高木式の食事改革が社会を変えた
高木兼寛が海軍で脚気の撲滅に成功したことは、一部の組織にとどまらず、日本全体の健康意識と医療制度にまで影響を及ぼしました。
彼の食事改革は、単なる現場の改善ではなく、社会全体に予防医療という新しい考え方を根付かせた大きな転換点でした。
その後の日本の栄養学への影響
海軍の食事に麦飯を導入するという高木の判断は、当時の常識を覆すものでした。そしてその実績は、徐々に医療界や教育現場へと広がっていきました。
脚気は明治期の日本において、「死に至る病」として恐れられていましたが、高木の成果によって、「食事内容の改善で病気は防げる」という考え方が注目されるようになります。
これが日本の栄養学研究の第一歩となり、後に「ビタミンB1欠乏が脚気の原因である」と科学的に証明される土壌を作ったのです。
さらに、高木の提唱した「バランスの取れた食事」は、戦後の学校給食制度にも取り入れられ、今の日本人の健康意識の基礎を築いたともいえます。
現代の健康意識に通じる思想とは?
高木が残した最大の功績は、「予防こそ最良の治療である」という思想でした。
現代では、生活習慣病やメタボリックシンドロームが社会問題として取り上げられていますが、それに対する対策の中心も「食生活の見直し」です。
高木のように「原因を科学的に突き止めて、それを生活に落とし込む」姿勢は、まさに現在の健康指導や食育の礎といえるでしょう。
また、彼の食事改革には「全員の命を守る」という明確な社会的視点がありました。高木は階級や立場に関係なく、すべての兵士に安全な食事を届けるべきだと考えたのです。
その視点は、現代における「誰ひとり取り残さない医療・健康づくり」の理念とも重なります。
【Q&A】高木兼寛と脚気に関する疑問
- Q高木兼寛はいつ生まれて、いつ亡くなったの?
- A
高木兼寛(たかぎ かねひろ)は、1849年(嘉永2年)に鹿児島で生まれ、1920年(大正9年)に亡くなりました。江戸から大正にかけて生きた、日本近代医学の草分けです。
- Q脚気ってどんな病気だったの?
- A
脚気(かっけ)は、ビタミンB1の欠乏によって起こる病気です。手足のしびれ、むくみ、心不全などを引き起こし、放置すれば死に至ることもありました。明治時代には日本海軍で多くの死者を出した深刻な問題でした。
- Qなぜ高木兼寛は評価されているの?
- A
高木兼寛は、科学的な実験と統計データをもとに「食事の違いが脚気の原因ではないか」と仮説を立て、実証しました。結果、海軍の脚気を激減させ、後の栄養学・予防医学の発展にもつながったため、近代医学の先駆者として高く評価されています。
【まとめ】科学で命を救った先駆者の生き方

高木兼寛は、目に見えない原因を相手に、根気よく仮説を立て、実験し、命を救う道を切り開いた人物です。
ビタミンという概念すらなかった時代に、食事と病気の関係にいち早く気づき、それを統計という科学的手法で証明しました。
彼の「まずやってみる」「結果で証明する」という姿勢は、現代の医療や科学だけでなく、社会全体の課題解決にも通じる考え方です。
今では当たり前のように語られる“予防医学”や“栄養管理”の原点には、こうした先駆者の挑戦があったことを、私たちは改めて知るべきではないでしょうか。
高木兼寛の功績は、今もなお、静かに私たちの暮らしを支え続けています。